現代社会学科・国際コミュニケーション学部:国境を越えた連携を通じて学び合う海洋プラごみ削減に向けたコミュニティベースの次世代育成プロジェクトに、卒業生を含む本学学生が多言語教育教材作成で参加します!
ニュース
現代社会学科の小林かおり准教授が代表を務める『海洋プラごみ「放出」と「漂着」における島嶼地域コミュニティベースの学び合いと国境を越えた次世代育成』プロジェクトがトヨタ財団国際助成に採択されました。
このプロジェクトは、西表島・セブ島・台湾といった三つの拠点間での国際連携に加え、各地域での産官学連携・地域連携・学術での文理融合アプローチに基づく海洋プラごみ削減に向けたプロジェクトです。
-

西表島の海洋ごみの状況(撮影:小林かおり)
-

フィリピンの海洋ごみの状況(撮影:小林かおり)
このプロジェクトに本学学生も多言語を使用した海洋環境教材を作成することで参加します。2023年度卒業した小林ゼミ学生が作成した「国境を越えて考えるSDGsすごろく」(試作版、日本語/ポルトガル語)をたたき台にして、海外でも使用できるように内容を改訂し、英語版(フィリピン)と中国語版(台湾)を作成します。
このプロジェクトへは、現在、本学に在籍している学生にとどまらず、本学卒業生も参加します。今回、英・中の改訂版を作成する際のリーダーは、国際コミュニケーション学部(現外国語学部)4年の松田朋佳さんです。
このプロジェクトへは、現在、本学に在籍している学生にとどまらず、本学卒業生も参加します。今回、英・中の改訂版を作成する際のリーダーは、国際コミュニケーション学部(現外国語学部)4年の松田朋佳さんです。
松田さん「日本以外の国や地域へ、この環境教育教材を共有できることを大変嬉しく思っていますが、同時に責任も感じています。仲間と協力し合いながら、より良い教材づくりを目指していきたいと思います。」
今夏、日本のプロジェクト拠点である西表島への調査を担当した、同じく国際コミュニケーション学部(現外国語学部)4年の浅井結衣さんは、昨年度、カンボジアでの女性支援プロジェクトにもリーダーとして参加しました。
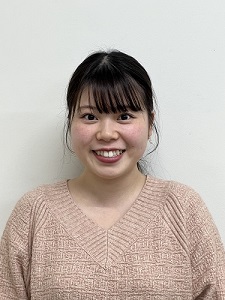
浅井さん「椙山には、日本の社会だけでなく海外ともつながれる活動があり、このような経験を学生時代にできることはとても貴重だと思っています。昨年度は、カンボジアでのインターン。今年は、教材づくりを通じたフィリピンと台湾との活動。これらの活動で得た実践力を社会でも生かせるようにしたいです。」
4年生が卒業後、この活動を引き継ぐのが、国際コミュニケーション学部(現外国語学部)3年の菊田歩花さんです。菊田さんも、今夏、プロジェクト拠点の一つである西表島での調査に参加し、その経験を活かし、教材づくりに携わります。

菊田さん「海外と共有できる教材づくりに参加することで、国際的な視点から持続可能な社会について深く学んでいきたいです。また、この体験を通じて、問題を多角的に捉える力・異文化理解・言語の多様性について知見を深めていき、異なる背景を持つ人たちと円滑に協力できるコミュニケーション力を向上させていきたいと考えています。この教材の引き継ぎから得た知識と経験を活かし、持続可能な社会の実現に積極的に貢献していき、次の代へと繋げていきたいです。」
また、この活動を裏方から支える一人が、2021年度国際コミュニケーション学部を卒業した宗田桃佳さんです。宗田さんは、在学時から社会貢献活動に興味をもち、本学の留学制度を利用して台湾へも留学していました。
宗田さん「大学在学中は椙山の制度を利用して台湾へ留学していました。今回、台湾ともかかわれる母校での国際プロジェクトに参加できてとてもうれしく思っています。国境を越えた海洋環境保全や次世代育成について陰ながら応援できるよう頑張りたいと思います。」
小林准教授が所属する情報社会学部現代社会学科では、国内にとどまらず、国境を越えた社会での実践プロジェクトにも参加できる機会を提供しています。

